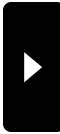2008年07月18日
kurabeのディナー
明日から三連休! さぁ!働くぞぉ~! と言うわけで、昨夜はイタリア料理教室のメンバーと、渡邊先生のお店kurabeへディナーに出かけた。(脈絡のない文章ですみません)
蔵を改造した2階が、アンティークな雰囲気の予約制レストランになっています。(頭上注意)

コース料理で、旬の食材を活かした美しい料理が、タイミングよく出されます。
私の拙い文章では、その美味しさを伝えきれませんので、写真をアップします。
前菜は3品。手前は新秋刀魚のマリネのバケットです。

サラダはホタテローストに、オレンジの絞り汁を加え、生野菜を乗せて、ホワイトグレープフルーツの酸味でいただきます。

オキダコに生マッシュルームを添え、ペコリーノチーズの塩味を効かせた、マリネの一皿です

夏バテ防止に、豚の肩ロース肉のハーブ焼きに、ゴルゴンゾーラのソースを添えて…

生パスタに完熟トマト、バジルを合わせ、オリーブオイルと塩味だけの冷製パスタ

キャラメルムースのデザートに旬の果物が美しく添えられていました

先生は出張料理もして下さるので、自宅に招いての本格的イタリアンが食べられます。
蔵を改造した2階が、アンティークな雰囲気の予約制レストランになっています。(頭上注意)

コース料理で、旬の食材を活かした美しい料理が、タイミングよく出されます。
私の拙い文章では、その美味しさを伝えきれませんので、写真をアップします。
前菜は3品。手前は新秋刀魚のマリネのバケットです。

サラダはホタテローストに、オレンジの絞り汁を加え、生野菜を乗せて、ホワイトグレープフルーツの酸味でいただきます。

オキダコに生マッシュルームを添え、ペコリーノチーズの塩味を効かせた、マリネの一皿です

夏バテ防止に、豚の肩ロース肉のハーブ焼きに、ゴルゴンゾーラのソースを添えて…

生パスタに完熟トマト、バジルを合わせ、オリーブオイルと塩味だけの冷製パスタ

キャラメルムースのデザートに旬の果物が美しく添えられていました

先生は出張料理もして下さるので、自宅に招いての本格的イタリアンが食べられます。
Posted by mahora at
12:04
│Comments(0)
2008年07月14日
蔵を訪ねて三千里
東京からのお客さまを、伊那市長谷黒河内(くろごうち)にある、蔵の宿「みらい塾」へご案内した。
この辺りの言葉で「おでい様」と呼ばれる、いわゆる旧家の母屋と蔵を改築して、宿泊施設として提供しています。
上伊那を代表する花、「アスルトロメリア」を大規模に栽培しているので、庭には四季の花々が咲き誇り、甘い香りと共に迎えてくれます。

女将さんの幸子さんは、「農林漁家民宿おかあさん100選」にも選ばれた、気さくでバイタリティ溢れる方です。
到着早々、母屋のサンルームで、女将お勧めのストロベリーとハイビスカスのフルーツティー、プルーンシャーベットをいただきます。

蔵の中はひんやりとして、外の暑さがウソのようです。

夕食は母屋の囲炉裏を囲んで、五平餅、岩魚の塩焼きなど、焼きたて熱々の郷土料理をいただきます。お料理はもちろん、女将さんの苦労を苦労と感じさせない明るい人がらで、楽しい会話が弾み、ビールも進みます。
アレコレと雑音も囁かれた中で、事成しえた人は、やはりどこか一本突き抜けています。

翌日は、イタリア料理教室でお世話になった渡辺先生のお店「kurabe」で、昼食用の生パスタとソースを求めました。
今週の木曜日に、料理教室の仲間たちと、先生のお店(蔵の2階が予約制のレストラン)で、打ち上げをすることになっているので、場所の確認も兼ねて行ってみました。

私が子どもの頃は、悪いことをしたり、親の言うことをきかないと、お仕置きのために暗い暗い「蔵の中」へ入れられたものです。
無機質なデジタル社会になると、古くて土臭い蔵も、こうして活用すれば、趣きのある癒しスポット(この言葉あまり好きでないけど…)に、変身です。
この辺りの言葉で「おでい様」と呼ばれる、いわゆる旧家の母屋と蔵を改築して、宿泊施設として提供しています。
上伊那を代表する花、「アスルトロメリア」を大規模に栽培しているので、庭には四季の花々が咲き誇り、甘い香りと共に迎えてくれます。

女将さんの幸子さんは、「農林漁家民宿おかあさん100選」にも選ばれた、気さくでバイタリティ溢れる方です。
到着早々、母屋のサンルームで、女将お勧めのストロベリーとハイビスカスのフルーツティー、プルーンシャーベットをいただきます。

蔵の中はひんやりとして、外の暑さがウソのようです。

夕食は母屋の囲炉裏を囲んで、五平餅、岩魚の塩焼きなど、焼きたて熱々の郷土料理をいただきます。お料理はもちろん、女将さんの苦労を苦労と感じさせない明るい人がらで、楽しい会話が弾み、ビールも進みます。
アレコレと雑音も囁かれた中で、事成しえた人は、やはりどこか一本突き抜けています。

翌日は、イタリア料理教室でお世話になった渡辺先生のお店「kurabe」で、昼食用の生パスタとソースを求めました。
今週の木曜日に、料理教室の仲間たちと、先生のお店(蔵の2階が予約制のレストラン)で、打ち上げをすることになっているので、場所の確認も兼ねて行ってみました。

私が子どもの頃は、悪いことをしたり、親の言うことをきかないと、お仕置きのために暗い暗い「蔵の中」へ入れられたものです。
無機質なデジタル社会になると、古くて土臭い蔵も、こうして活用すれば、趣きのある癒しスポット(この言葉あまり好きでないけど…)に、変身です。
Posted by mahora at
11:59
│Comments(0)
2008年07月10日
美しきカブール
映画「君のためなら千回でも」
ラブストーリーを想わせる、ロマンチックなタイトルからは想像できない、人間の内面に潜む非情さ、愚かさ、世の不条理を見せつけられる映画だった。

ガソリンや食料品が高騰しているっ! と文句を言っても、とりあえず、戦争で生命の危険に晒されることもなく、今夜、食べるモノにも窮することのないこの国では、どこか遠い遠い世界のできごとのように思えてしまう。
ずいぶん前に、「アフガニスタンの星を見上げて」と言う本を読んだことがあるが、内容がまったく思い出せないっ!人はすぐに忘れるんだっ! そして、同じ過ちを繰り返す。
無能な政治家と、大国のエゴに翻弄される運命はごめんですっ!
撮影のため、中国ウイグル地区に再現したカブールの街が、エキゾチックで美しくかった。
ラブストーリーを想わせる、ロマンチックなタイトルからは想像できない、人間の内面に潜む非情さ、愚かさ、世の不条理を見せつけられる映画だった。

ガソリンや食料品が高騰しているっ! と文句を言っても、とりあえず、戦争で生命の危険に晒されることもなく、今夜、食べるモノにも窮することのないこの国では、どこか遠い遠い世界のできごとのように思えてしまう。
ずいぶん前に、「アフガニスタンの星を見上げて」と言う本を読んだことがあるが、内容がまったく思い出せないっ!人はすぐに忘れるんだっ! そして、同じ過ちを繰り返す。
無能な政治家と、大国のエゴに翻弄される運命はごめんですっ!
撮影のため、中国ウイグル地区に再現したカブールの街が、エキゾチックで美しくかった。
Posted by mahora at
10:49
│Comments(0)
2008年07月08日
思い出の花かご
仕事関係で8年間、当市に在住された方が、関西のご実家へ帰られることになり、わざわざご挨拶に出向いて下さった。
そのうえ、趣味のフラワーアレンジメントで、豪華で素敵な花かごまでプレゼントして下さった。
お世話になったお礼ですっ! イエイエ、とんでもないですっ!

伊那市は住みやすく、思い出多く、名残惜しくて、引越しの荷造りも、なかなかはかどらないとか…
伊那市民としてはそう言って下さるだけで、嬉しい限りです。
どうぞ、お身体を大切にお健やかに、そして、いつでも遊びに来て下さいね。
そのうえ、趣味のフラワーアレンジメントで、豪華で素敵な花かごまでプレゼントして下さった。
お世話になったお礼ですっ! イエイエ、とんでもないですっ!
伊那市は住みやすく、思い出多く、名残惜しくて、引越しの荷造りも、なかなかはかどらないとか…
伊那市民としてはそう言って下さるだけで、嬉しい限りです。
どうぞ、お身体を大切にお健やかに、そして、いつでも遊びに来て下さいね。
Posted by mahora at
13:20
│Comments(0)
2008年07月05日
プロが伝授する旨味の作り方
最後のイタリア料理教室は、先生の原点となったフレンチの家庭料理「鶏肉のプロヴァンス風」でした。
塩コショウ、ヴァージンオイル、白ワインでマリネした、鶏肉をフライパンで焼き色をつけます。
これが、加熱調理のコツの「集中型」です。

パイ皿に肉を取り出し、酸味と塩味を中心に白ワインで醸造したディジョンマスタードをタップリ塗ります。味を決定づける隠し味ですっ!

生パン粉に、タイム・ローズマリー・パセリ・ペコリーノチーズを刻み混ぜ、ガーリックオイルを加えた香草パン粉を肉片が隠れるまで塗ります。キャーッ! うまそぅ~!

200度のオーブンで10分ほど焼き上げます。これが加熱調理のコツの「抽出型」です。
先生のお店「kurabe」特性のトマトソースの上に、肉を盛りつけ、トマトのコンカッセ(7ミリ四方のトマトの角切りです)をのせ、澄ましバターと、ヴァージンオイルを振ってできあがりです。

塩コショウ、ヴァージンオイル、白ワインでマリネした、鶏肉をフライパンで焼き色をつけます。
これが、加熱調理のコツの「集中型」です。

パイ皿に肉を取り出し、酸味と塩味を中心に白ワインで醸造したディジョンマスタードをタップリ塗ります。味を決定づける隠し味ですっ!

生パン粉に、タイム・ローズマリー・パセリ・ペコリーノチーズを刻み混ぜ、ガーリックオイルを加えた香草パン粉を肉片が隠れるまで塗ります。キャーッ! うまそぅ~!

200度のオーブンで10分ほど焼き上げます。これが加熱調理のコツの「抽出型」です。
先生のお店「kurabe」特性のトマトソースの上に、肉を盛りつけ、トマトのコンカッセ(7ミリ四方のトマトの角切りです)をのせ、澄ましバターと、ヴァージンオイルを振ってできあがりです。

Posted by mahora at
14:18
│Comments(0)
2008年06月27日
狂った水の美味しさ
イタリア料理教室も、パスタ・ピッツァ・ニョッキの定番から、魚・肉料理にグレードアップ!
昨夜は、漁師さんのまかないが始まりの「アクア・パッツァ」をレクチャーしていただいた。
活きのいい鯵(アジ)を使い、腹から頭に包丁を入れ、エラから尾に向かって、はらわたをきれいに取り除き、塩コショウで下味をつける。
この時、プロは生臭さとエグっぽさを残さないため、身を崩さないように血合いも一気に取り除いてしまう。

実際にやってみたけど、主婦歴何十年の人でも、なかなかできない…と言うか、まず切り身の魚しか購入しないから、これは明らかに経験不足です。
炎が立つくらいに熱したフライパンにオリーブオイルを入れ、焦がすのではなく、狐色に焼き色をつける。焦げ目と焼き色は違うっ!

フライパンの中に、白ワインを一気に入れると、泡立つように沸騰し、アルコール分が飛んでいく。
この様子が狂った水のようで、アクア・パッツァの語源となったそうです。

トマト・にんにく・刻みパセリ・アサリを入れ、フタをして中火で蒸し焼きにする。
彩りも鮮やかで、お腹の虫が鳴きそうな香りが、キッチン中に立ちこめます。

まず、魚を取り出し、残った具とスープにタップリのオリーブオイルを入れ、乳化させる。
この料理は魚だけでなく、スープも一緒に楽しむ料理だそうです。
アジと言えば、塩焼き・あんかけ・フライぐらいだけど、身近な材料で「わぁ~!ごちそう!」と、思わず身の乗り出したくレシピでした。

昨夜は、漁師さんのまかないが始まりの「アクア・パッツァ」をレクチャーしていただいた。
活きのいい鯵(アジ)を使い、腹から頭に包丁を入れ、エラから尾に向かって、はらわたをきれいに取り除き、塩コショウで下味をつける。
この時、プロは生臭さとエグっぽさを残さないため、身を崩さないように血合いも一気に取り除いてしまう。

実際にやってみたけど、主婦歴何十年の人でも、なかなかできない…と言うか、まず切り身の魚しか購入しないから、これは明らかに経験不足です。
炎が立つくらいに熱したフライパンにオリーブオイルを入れ、焦がすのではなく、狐色に焼き色をつける。焦げ目と焼き色は違うっ!

フライパンの中に、白ワインを一気に入れると、泡立つように沸騰し、アルコール分が飛んでいく。
この様子が狂った水のようで、アクア・パッツァの語源となったそうです。

トマト・にんにく・刻みパセリ・アサリを入れ、フタをして中火で蒸し焼きにする。
彩りも鮮やかで、お腹の虫が鳴きそうな香りが、キッチン中に立ちこめます。

まず、魚を取り出し、残った具とスープにタップリのオリーブオイルを入れ、乳化させる。
この料理は魚だけでなく、スープも一緒に楽しむ料理だそうです。
アジと言えば、塩焼き・あんかけ・フライぐらいだけど、身近な材料で「わぁ~!ごちそう!」と、思わず身の乗り出したくレシピでした。

Posted by mahora at
11:13
│Comments(0)
2008年06月20日
くちどけニョッキ
週に一度の、待ち遠しいイタリア料理教室の3回目。
昨夜は「ジャガイモのニョッキ、ローズマリー風味のクリームソース」と、ギスギスした今の世の中に、一番不足している、優しさと気品溢れるレシピでした。
ジャガイモの風味がしっかり残り、これまでのニョッキの概念を覆すような、フワッとした食感と口当たりまろやかな、とろけるようなニョッキでした。

■ジャガイモは沸いた湯から茹でる
■ジャガイモには下味をきちんとつける
■卵はよく溶いておく
■裏ごしは上から下に押しつけ、しゃもじを引いて裏ごしてはいけない
■とにかく生地を練ってはいけない
火の通りが均一になるように、ソースが絡むように、成形します

茹で上がったニュッキはすばやく冷水で冷やす

クリームソースはできあがりの濃度をイメージして、煮詰めすぎないこと。ローズマリーの香りが広がり、至福の時が…

トマトとバジルの彩りが爽やかな、冷製トマトソースニョッキ。トマトが完熟してないので、ペコリーノチーズで味に変化を…

昨夜は「ジャガイモのニョッキ、ローズマリー風味のクリームソース」と、ギスギスした今の世の中に、一番不足している、優しさと気品溢れるレシピでした。
ジャガイモの風味がしっかり残り、これまでのニョッキの概念を覆すような、フワッとした食感と口当たりまろやかな、とろけるようなニョッキでした。

■ジャガイモは沸いた湯から茹でる
■ジャガイモには下味をきちんとつける
■卵はよく溶いておく
■裏ごしは上から下に押しつけ、しゃもじを引いて裏ごしてはいけない
■とにかく生地を練ってはいけない
火の通りが均一になるように、ソースが絡むように、成形します

茹で上がったニュッキはすばやく冷水で冷やす

クリームソースはできあがりの濃度をイメージして、煮詰めすぎないこと。ローズマリーの香りが広がり、至福の時が…

トマトとバジルの彩りが爽やかな、冷製トマトソースニョッキ。トマトが完熟してないので、ペコリーノチーズで味に変化を…

Posted by mahora at
11:46
│Comments(0)
2008年06月19日
地方に咲く花
道交法改正で、高齢者ドライバーへのもみじマーク表示が、義務づけられました。
運転中、注意してみていると、すれちがう車の10台に3台くらいは、もみじマークです。
高齢者予備群としては、他人事ではなく、もみじマークは増えることはあっても、減ることはないっ!
逆に、初心者の若葉マークは、減ることはあっても増えることはないだろうなぁ…と思う。
週末、東京へ行ったけど、電車の中では、妊娠中であることを示すホルダーを、バッグにつけている人が目立った。
日本の人口の10分の1が集まっているので、少子化とは言え、新しい命の誕生する確立も高いわけですね。
こうしたところにも、都市と地方の格差が…

運転中、注意してみていると、すれちがう車の10台に3台くらいは、もみじマークです。
高齢者予備群としては、他人事ではなく、もみじマークは増えることはあっても、減ることはないっ!
逆に、初心者の若葉マークは、減ることはあっても増えることはないだろうなぁ…と思う。
週末、東京へ行ったけど、電車の中では、妊娠中であることを示すホルダーを、バッグにつけている人が目立った。
日本の人口の10分の1が集まっているので、少子化とは言え、新しい命の誕生する確立も高いわけですね。
こうしたところにも、都市と地方の格差が…

Posted by mahora at
14:44
│Comments(0)
2008年06月13日
愛しのマルゲリータ
イタリア料理教室の2回目。
昨夜はフォカッチャとピッツァ・マルゲリータで、イースト発酵やら、練り込みなど思いのほかハードで、終わったら10時を回っていた。
前回同様、惚れ惚れするくらいの手際の良さと、無駄のない動きで、kurabeオーナーシェフの渡辺先生が、ポイントを押さえながら、デモをして見せてくれる。

フォカッチャも、それから派生したピッツァも、小麦粉本来の味と香りを十分に味わってもらいたい、と言う先生の意向で、kurabe流の石臼挽きの県内産地粉と、全粒粉をブレンドしたものを用意して下さった。
めん棒を使って生地を丸く伸ばすコツや、菊の花のように、らせん状に生地を練り込んでガス抜きをする菊練りなど、その理にかなった動きに、思わず「ほほっう!」と、唸ってしまう。

1人300グラムの地粉が用意されたので、フォカッチャもマルゲリータも食べきれず、持ち帰りができるほどだった。満足! 満足!

昨夜はフォカッチャとピッツァ・マルゲリータで、イースト発酵やら、練り込みなど思いのほかハードで、終わったら10時を回っていた。
前回同様、惚れ惚れするくらいの手際の良さと、無駄のない動きで、kurabeオーナーシェフの渡辺先生が、ポイントを押さえながら、デモをして見せてくれる。

フォカッチャも、それから派生したピッツァも、小麦粉本来の味と香りを十分に味わってもらいたい、と言う先生の意向で、kurabe流の石臼挽きの県内産地粉と、全粒粉をブレンドしたものを用意して下さった。
めん棒を使って生地を丸く伸ばすコツや、菊の花のように、らせん状に生地を練り込んでガス抜きをする菊練りなど、その理にかなった動きに、思わず「ほほっう!」と、唸ってしまう。

1人300グラムの地粉が用意されたので、フォカッチャもマルゲリータも食べきれず、持ち帰りができるほどだった。満足! 満足!

Posted by mahora at
10:45
│Comments(0)
2008年06月11日
苦悩の贋札
今年のアメリカアカデミー賞、外国語映画賞受賞の「ヒトラーの贋札」

第二次大戦中、ナチスドイツから強制的に贋札造りに従事させられたユダヤ人の目を通して、戦争の愚かさと理不尽、自身の命と人としての正義、ユダヤ民族としての尊厳と誇りの中で、苦悩する姿が描かれていた。
バックに流れる甘く切ないタンゴの調べが、贋札を造り続けることでしか生きのびられないと言う、選択の余地がない絶望的な現実とマッチし、余計に哀しくなってしまった。
50年以上も前の時代、他国の贋札を大量に作って、経済を混乱させ、戦況を有利にしようと企んだ「ベルンハルト作戦」
戦争は人間を、あらゆる面で暴力的にしてしまう。
今、世界中で起こっている原油や食物高騰だって、元はアメリカのイラク戦争が原因だっ!!

第二次大戦中、ナチスドイツから強制的に贋札造りに従事させられたユダヤ人の目を通して、戦争の愚かさと理不尽、自身の命と人としての正義、ユダヤ民族としての尊厳と誇りの中で、苦悩する姿が描かれていた。
バックに流れる甘く切ないタンゴの調べが、贋札を造り続けることでしか生きのびられないと言う、選択の余地がない絶望的な現実とマッチし、余計に哀しくなってしまった。
50年以上も前の時代、他国の贋札を大量に作って、経済を混乱させ、戦況を有利にしようと企んだ「ベルンハルト作戦」
戦争は人間を、あらゆる面で暴力的にしてしまう。
今、世界中で起こっている原油や食物高騰だって、元はアメリカのイラク戦争が原因だっ!!
Posted by mahora at
14:06
│Comments(0)
2008年06月06日
イタリアンシェフのコツ
伊那芸術文化協会が主催する「イタリア料理教室-シェフがこっそり教えるプロのコツ」の1回目。
20名の定員がすぐ満杯になる人気の講座で、講師は市内で生パスタとソースの製造販売をしているお店、kurabe(くらべ)の渡辺シェフです。
北フランスで修行し、ホテルフレンチに満足せず、イタリアンに目覚め、主食となるパスタを一から作ってみたい…と言うこだわりの持ち主で、最近では地元企業タカノと協力して、韃靼そばのそば粉を混ぜた、生パスタにも挑戦している、イケメンシェフです。

昨夜はトマトソースの基本となる、ポロドーロソースと、アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ(1回で入力できん!)でした。
玉ねぎ・ニンジン・セロリをガーリックオイルで、ゆっくりじっくり、ゆっくりじっくり、本当にゆぅ~っくり!じぃ~っくり!と炒め、香味野菜の旨味を引き出しソフリットにする過程を、実演してくれました。

■火力調節は火を弱めるより、ガス台から外すことで加熱をおさえる
■焦がすのではなく、焼き色をつけ、香ばしさと野菜の甘さを引き出す(これはかなり根気がいる)
■鍋肌についた、焼きつきをこそげ落とすことで、旨味が増す
■旨味と塩味を舌でしっかり覚え、それぞれ切り離して考えるクセをつける(これは修行あるのみ)
など、その手際のよい、ムダのない動きの中で、ポイントを分かりやすく説明してくれる。
すべてにおいて言えることだけど、基本がしっかりしていればバリエーションは限りなく広がり、厚みを帯びて味わい深くなる。

上はパセリのみじん切りの実演。広がらず散らからず、茎だけを残して簡単にみじん切りができる方法を伝授。プロはやはり違うっ! と実感した。
実演のあとは、5人一組でペペロンチーノを実習し、試食した。
先生の生パスタのせいか、季節の食材の、春キャベツとの食感がオイルとマッチし、とっても美味しくできた。
写真は先生が作ったペペロンチーノです!

20名の定員がすぐ満杯になる人気の講座で、講師は市内で生パスタとソースの製造販売をしているお店、kurabe(くらべ)の渡辺シェフです。
北フランスで修行し、ホテルフレンチに満足せず、イタリアンに目覚め、主食となるパスタを一から作ってみたい…と言うこだわりの持ち主で、最近では地元企業タカノと協力して、韃靼そばのそば粉を混ぜた、生パスタにも挑戦している、イケメンシェフです。

昨夜はトマトソースの基本となる、ポロドーロソースと、アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ(1回で入力できん!)でした。
玉ねぎ・ニンジン・セロリをガーリックオイルで、ゆっくりじっくり、ゆっくりじっくり、本当にゆぅ~っくり!じぃ~っくり!と炒め、香味野菜の旨味を引き出しソフリットにする過程を、実演してくれました。

■火力調節は火を弱めるより、ガス台から外すことで加熱をおさえる
■焦がすのではなく、焼き色をつけ、香ばしさと野菜の甘さを引き出す(これはかなり根気がいる)
■鍋肌についた、焼きつきをこそげ落とすことで、旨味が増す
■旨味と塩味を舌でしっかり覚え、それぞれ切り離して考えるクセをつける(これは修行あるのみ)
など、その手際のよい、ムダのない動きの中で、ポイントを分かりやすく説明してくれる。
すべてにおいて言えることだけど、基本がしっかりしていればバリエーションは限りなく広がり、厚みを帯びて味わい深くなる。

上はパセリのみじん切りの実演。広がらず散らからず、茎だけを残して簡単にみじん切りができる方法を伝授。プロはやはり違うっ! と実感した。
実演のあとは、5人一組でペペロンチーノを実習し、試食した。
先生の生パスタのせいか、季節の食材の、春キャベツとの食感がオイルとマッチし、とっても美味しくできた。
写真は先生が作ったペペロンチーノです!

Posted by mahora at
11:21
│Comments(0)
2008年06月05日
文豪の古里馬籠
かつて長野県だった木曽馬籠宿は、すったもんだの末の平成の大合併により、岐阜県中津川市になった。

「但馬屋」は、木曽十一宿最南端の馬籠宿の中にある、古民家造りの心温まる静かな宿です。
自家栽培の米や野菜を使った、素朴で味わい深い郷土料理を中心に提供しています。

食後は囲炉裏端で、ご主人から、民謡木曽節と、木曽踊りの手ほどきを受けられます。
哀愁を帯びた木曽節に合わせ、かつての旅人のように、囲炉裏を囲んで踊ります。
そして、木曽踊習得証書なるものもいただけます。
ここは文豪島崎藤村の古里で、近くには菩提寺の永昌寺もあり、藤村の墓もあります。
「夜明け前」の一節が刻まれた碑がある展望台に登れば、恵那山と中津川市が手にとるような、素晴らしい眺望が望めます。


「但馬屋」は、木曽十一宿最南端の馬籠宿の中にある、古民家造りの心温まる静かな宿です。
自家栽培の米や野菜を使った、素朴で味わい深い郷土料理を中心に提供しています。

食後は囲炉裏端で、ご主人から、民謡木曽節と、木曽踊りの手ほどきを受けられます。
哀愁を帯びた木曽節に合わせ、かつての旅人のように、囲炉裏を囲んで踊ります。
そして、木曽踊習得証書なるものもいただけます。
ここは文豪島崎藤村の古里で、近くには菩提寺の永昌寺もあり、藤村の墓もあります。
「夜明け前」の一節が刻まれた碑がある展望台に登れば、恵那山と中津川市が手にとるような、素晴らしい眺望が望めます。

Posted by mahora at
13:13
│Comments(0)
2008年06月04日
釜飯の鳥鍵
中仙道・木曽福島の「鳥鍵(とりかぎ)」
釜飯や鰻料理が評判のお店です。
前もって予約しておくと、奥座敷に案内してくれます。

寂しいくらいに静かで、レトロで風情ある雰囲気の奥座敷でいただく、釜飯や鰻重は一味違います。
旅の道中で密談? するにはもってこいのお店です。

釜飯や鰻料理が評判のお店です。
前もって予約しておくと、奥座敷に案内してくれます。

寂しいくらいに静かで、レトロで風情ある雰囲気の奥座敷でいただく、釜飯や鰻重は一味違います。
旅の道中で密談? するにはもってこいのお店です。

Posted by mahora at
14:28
│Comments(0)
2008年06月02日
まちの案内人は人生の案内人
天井知らずのガソリン価格に対抗して、友人と木曽中仙道を歩く旅にでた。
…と言っても歩いたのは、木曽福島宿を2時間ほどですが…
で、街のことは街の住人に訊け! の王道にのっとり、まちづくり木曽福島が運営するまちの案内人をお願いした。
古い町並みや豊かな自然、歴史と文化のある伝統工芸に至るまで、一緒に歩いて説明してくれる。
当日はあいにくの雨降りだったけど、案内人の三村さんと、親水公園で待ち合わせた。

木曽漆器発祥の地「よし彦」前を通り、中八沢橋から当時の宿場町が保存されている上の段エリアに入り、江戸時代にタイムスリップする。
「漆の館」では、三村さんのご配慮により、途絶えていた伝統の矢澤春慶塗りを現代に蘇らせ、後世に伝えようとしているご主人から、引き締った風格の作品と一緒に、漆についての貴重なお話を聞かせていただく。
奥さまからは、ホッとする美味しいお茶のおもてなしまで受けてしまった。

「木地の館篠原」では、東京からアイターンされた松本さんが、九十歳を超えた師匠の、この見事な卓越した技を途切れさせてはいけないと、数々の作品と共に、ご自身の想いを熱く語って下さり、その情熱に感心するばかり…

電柱の地中化により、スッキリした町並みの至る所には、三村さんが子どもの頃から変わらない、水の流れがそのまま存在していた。
武田信玄の娘、真理姫の供養塔がある大通寺へ通ずる、なまこ壁の土蔵の景色を眺めていると、今にも、ちょんまげ姿のお侍が現れてきそうです。

陰陽師安倍清明伝説にまつわる清明社と、観光文化会館を見学し、馬宿小路を抜け、再び親水公園に下りてくる。
町民の寄付によって創られた、風情ある行人橋歩道橋を渡り、清らかな木曽川の流れを眺めながら、整備された遊歩道を山村代官屋敷に向かう。
三村さんからは子どもの頃、川で魚を釣ったり、泳いだり、崖家造りの家並みなど、住民の生活にとって、この木曽川が大切な存在であることがうかがわれる。

文豪島崎藤村の夜明け前の碑がある、レトロな建物「木曽郷土館」を眺めながら、代官屋敷に到着したでござる(ここでなぜか、武士語になる)
長きにわたって木曽の地を治めた、山村家の屋敷の一部を整備開放した施設で、当時の貴重な資料を元に、その人となりを丁寧に説明してくださる。
民のことを第一に政を行った代官らしく、質素で簡素なスッキリした造りです。
庭からは守り神とされた狐のミイラが発見され、屋敷内にある山村稲荷に、ご神体として祀られ、そのミイラもありがたく拝ませていただいた。
こうしたなさそうでありそうな、摩訶不思議な伝説は、旅をいっそう非日常的な空間へ誘い、実に愉快でござる。

最後に三村さんから、今日の出逢いの記念にと、木曽の山々に響きわたるような伸び伸びした声で、民謡「木曽節」のプレゼントがあり、一同大感激するでござる。

時間オーバーの2時間の案内で、料金はたったの弐千円のうえ、宿泊先の馬籠までの道案内もして下さり、誠にかたじけなく候。
後期高齢者である三村さんですが、古里の町を心から愛され、活き活きと、前向きに生きておられる姿は、まちの案内人であると同時に、人生の先達としての案内人でした。
旅はやはりこうした思いがけない出逢いが、想い出になるのです。
…と言っても歩いたのは、木曽福島宿を2時間ほどですが…
で、街のことは街の住人に訊け! の王道にのっとり、まちづくり木曽福島が運営するまちの案内人をお願いした。
古い町並みや豊かな自然、歴史と文化のある伝統工芸に至るまで、一緒に歩いて説明してくれる。
当日はあいにくの雨降りだったけど、案内人の三村さんと、親水公園で待ち合わせた。

木曽漆器発祥の地「よし彦」前を通り、中八沢橋から当時の宿場町が保存されている上の段エリアに入り、江戸時代にタイムスリップする。
「漆の館」では、三村さんのご配慮により、途絶えていた伝統の矢澤春慶塗りを現代に蘇らせ、後世に伝えようとしているご主人から、引き締った風格の作品と一緒に、漆についての貴重なお話を聞かせていただく。
奥さまからは、ホッとする美味しいお茶のおもてなしまで受けてしまった。

「木地の館篠原」では、東京からアイターンされた松本さんが、九十歳を超えた師匠の、この見事な卓越した技を途切れさせてはいけないと、数々の作品と共に、ご自身の想いを熱く語って下さり、その情熱に感心するばかり…

電柱の地中化により、スッキリした町並みの至る所には、三村さんが子どもの頃から変わらない、水の流れがそのまま存在していた。
武田信玄の娘、真理姫の供養塔がある大通寺へ通ずる、なまこ壁の土蔵の景色を眺めていると、今にも、ちょんまげ姿のお侍が現れてきそうです。

陰陽師安倍清明伝説にまつわる清明社と、観光文化会館を見学し、馬宿小路を抜け、再び親水公園に下りてくる。
町民の寄付によって創られた、風情ある行人橋歩道橋を渡り、清らかな木曽川の流れを眺めながら、整備された遊歩道を山村代官屋敷に向かう。
三村さんからは子どもの頃、川で魚を釣ったり、泳いだり、崖家造りの家並みなど、住民の生活にとって、この木曽川が大切な存在であることがうかがわれる。

文豪島崎藤村の夜明け前の碑がある、レトロな建物「木曽郷土館」を眺めながら、代官屋敷に到着したでござる(ここでなぜか、武士語になる)
長きにわたって木曽の地を治めた、山村家の屋敷の一部を整備開放した施設で、当時の貴重な資料を元に、その人となりを丁寧に説明してくださる。
民のことを第一に政を行った代官らしく、質素で簡素なスッキリした造りです。
庭からは守り神とされた狐のミイラが発見され、屋敷内にある山村稲荷に、ご神体として祀られ、そのミイラもありがたく拝ませていただいた。
こうしたなさそうでありそうな、摩訶不思議な伝説は、旅をいっそう非日常的な空間へ誘い、実に愉快でござる。

最後に三村さんから、今日の出逢いの記念にと、木曽の山々に響きわたるような伸び伸びした声で、民謡「木曽節」のプレゼントがあり、一同大感激するでござる。

時間オーバーの2時間の案内で、料金はたったの弐千円のうえ、宿泊先の馬籠までの道案内もして下さり、誠にかたじけなく候。
後期高齢者である三村さんですが、古里の町を心から愛され、活き活きと、前向きに生きておられる姿は、まちの案内人であると同時に、人生の先達としての案内人でした。
旅はやはりこうした思いがけない出逢いが、想い出になるのです。
Posted by mahora at
14:02
│Comments(0)
2008年05月28日
辞めたその後…
城 繁幸「3年で辞めた若者はどこへ行ったのか-アウトサイダーの時代」ちくま新書
平成生まれの成人が登場する現代、世界はますます混沌とし、平和と繁栄は遠のくばかり。
未曾有の少子高齢化社会を迎える、極東アジアの小国に至っては、国民総ネガティブ思考で、麗しい才色兼備のフリーアナウンサーまで、自死してしまう。
あぁ! 若者よ! もっと未来に希望を持とうよ! とゲキを飛ばすのは簡単だけど、その希望はどこにあるの? と問われれば、かえす言葉がありません。
著者は昭和的価値観に縛られ、既存システムの維持に必死になり、既得権のうえにあぐらをかき、真の実力主義におびえる人びとを痛烈に批判しています。
その典型として、新聞、テレビ、雑誌などのメディアを挙げ、日本のメディアは世界一レベルが低い! と切って捨てています。(非常に説得力があります)
そして、自らの意思で、これまでの日本型システムのレールから下り、新しい平成的価値観を創造し、行動し始めた若者たちをとり上げ、温かいまなざしでエールを送っています。
著者自身が、73年生まれのロスジェネ世代ですが、いつの時代も、未来の扉を開くのはやはり若者たちです。

平成生まれの成人が登場する現代、世界はますます混沌とし、平和と繁栄は遠のくばかり。
未曾有の少子高齢化社会を迎える、極東アジアの小国に至っては、国民総ネガティブ思考で、麗しい才色兼備のフリーアナウンサーまで、自死してしまう。
あぁ! 若者よ! もっと未来に希望を持とうよ! とゲキを飛ばすのは簡単だけど、その希望はどこにあるの? と問われれば、かえす言葉がありません。
著者は昭和的価値観に縛られ、既存システムの維持に必死になり、既得権のうえにあぐらをかき、真の実力主義におびえる人びとを痛烈に批判しています。
その典型として、新聞、テレビ、雑誌などのメディアを挙げ、日本のメディアは世界一レベルが低い! と切って捨てています。(非常に説得力があります)
そして、自らの意思で、これまでの日本型システムのレールから下り、新しい平成的価値観を創造し、行動し始めた若者たちをとり上げ、温かいまなざしでエールを送っています。
著者自身が、73年生まれのロスジェネ世代ですが、いつの時代も、未来の扉を開くのはやはり若者たちです。

Posted by mahora at
10:56
│Comments(0)
2008年05月20日
すなおバカ
公共機関主催の、とある研修会に出席させてもらった。
10人ほどのワークショップ形式で、ある課題について討議した。
話し合った課題目標を、記録係に指名された人が、用紙にマジックで大きく書き、メンバーに見せた。
「心も身体も巧しく……○○○」
あれっ? んっ?
確か、「巧しく」は「逞しく」じゃないのかいっ?
書いた人は、某自治体職員である。
私以外はみな、20代のピチピチの若者ばかり…
メンバーの中で、ただ一人、五十を過ぎて浮いているオバサンは、遠慮しながら、勇気を出して、謙虚に指摘した。
反応は…
「えぇ~! わかんなぁ~いっ!」と言いながら、携帯電話で変換し始めた。
「うわ~ぉ! 変換できないっ!」(ほんとかよっ!)
結末は
不確かなもの、自信のないものは、とりあえず「ひらがな」表記でと言うことで落ち着いた。
あぁ! とうとう、やってしまったかっ! ゆとり教育っ!
今週のAERAに、ブレイクするおバカキャラは、サバイバル社会での「負け組たちのヒーロー」だとか…
分からないものは、分かりません! 知らないものは、知りません! だから、どうぞ、教えて下さい!
この謙虚さが魅力の、すなおバカと言う、憎めない新しい人種らしいです。

10人ほどのワークショップ形式で、ある課題について討議した。
話し合った課題目標を、記録係に指名された人が、用紙にマジックで大きく書き、メンバーに見せた。
「心も身体も巧しく……○○○」
あれっ? んっ?
確か、「巧しく」は「逞しく」じゃないのかいっ?
書いた人は、某自治体職員である。
私以外はみな、20代のピチピチの若者ばかり…
メンバーの中で、ただ一人、五十を過ぎて浮いているオバサンは、遠慮しながら、勇気を出して、謙虚に指摘した。
反応は…
「えぇ~! わかんなぁ~いっ!」と言いながら、携帯電話で変換し始めた。
「うわ~ぉ! 変換できないっ!」(ほんとかよっ!)
結末は
不確かなもの、自信のないものは、とりあえず「ひらがな」表記でと言うことで落ち着いた。
あぁ! とうとう、やってしまったかっ! ゆとり教育っ!
今週のAERAに、ブレイクするおバカキャラは、サバイバル社会での「負け組たちのヒーロー」だとか…
分からないものは、分かりません! 知らないものは、知りません! だから、どうぞ、教えて下さい!
この謙虚さが魅力の、すなおバカと言う、憎めない新しい人種らしいです。

Posted by mahora at
12:17
│Comments(0)
2008年05月14日
お散歩ブラブラ転々と
三木聡監督、オダギリジョー主演の映画 「転々」が、昨夜の例会。
この組み合わせは、深夜TV番組「時効警察」のコンビとか…
プレスにそう書いてあった…

直木賞作品の映画化らしいけど、回りくどいと言うか、フラフラと脱力しながら、愛と幸せを探し求める若者よりは、もっと貪欲にギラギラする求道者の方が、なんか好きだなぁ…
劇中、街中で岸部一徳に逢うと良いことがあるっ! と言う、都市伝説を設定している。
こう言うのは、文句なく好きですっ!
この組み合わせは、深夜TV番組「時効警察」のコンビとか…
プレスにそう書いてあった…

直木賞作品の映画化らしいけど、回りくどいと言うか、フラフラと脱力しながら、愛と幸せを探し求める若者よりは、もっと貪欲にギラギラする求道者の方が、なんか好きだなぁ…
劇中、街中で岸部一徳に逢うと良いことがあるっ! と言う、都市伝説を設定している。
こう言うのは、文句なく好きですっ!
Posted by mahora at
14:32
│Comments(0)
2008年05月12日
慈愛のケーキ
JR伊那北駅前の洋菓子店、フランセ板屋の母の日オリジナルケーキ。
ホワイトチョコを、薄いサーモンピンクに色づけして、カーネーションに見立ててデコしている。
まるで私のような(?)、心優しい慈愛に満ちた母をイメージさせ、見ているだけで穏やかな気分になれる。

崩れそうなくらいふんわり仕上げたスポンジに、初夏らしい爽やかな酸味のラズベリームースをサンドし、クリームチーズを入れた生クリームで、スッキリとコーティングしている。
このクリームが、甘さだけに陥らないよう、アクセントになっていて、優しいけれど叱る時は叱るっ! そんな品格ある日本のおかあちゃんの味になっていた。
ホワイトチョコを、薄いサーモンピンクに色づけして、カーネーションに見立ててデコしている。
まるで私のような(?)、心優しい慈愛に満ちた母をイメージさせ、見ているだけで穏やかな気分になれる。

崩れそうなくらいふんわり仕上げたスポンジに、初夏らしい爽やかな酸味のラズベリームースをサンドし、クリームチーズを入れた生クリームで、スッキリとコーティングしている。
このクリームが、甘さだけに陥らないよう、アクセントになっていて、優しいけれど叱る時は叱るっ! そんな品格ある日本のおかあちゃんの味になっていた。
Posted by mahora at
09:54
│Comments(0)
2008年05月10日
私のなまえ
部屋を片付けていたら、娘が中学校の家庭科で作った、限りなくミッフィーに似た、ウサギの指人形が出てきた。
肌触りのよい白のタオル地を使い、赤ちゃんが遊ぶことを考えて、目玉のボタンもしっかりくくり付け、ボンドで留めてある。

胸についた名札に「ようこ」という、なまえが書いてあった。
ようこっていったい誰?
肌触りのよい白のタオル地を使い、赤ちゃんが遊ぶことを考えて、目玉のボタンもしっかりくくり付け、ボンドで留めてある。

胸についた名札に「ようこ」という、なまえが書いてあった。
ようこっていったい誰?
Posted by mahora at
16:18
│Comments(0)
2008年05月09日
安らかな精霊
実家の菩提寺は、飯田市の善勝寺で、幼稚園から高校・短大まである、学校法人「高松学園」も経営している。
飯田女子高校は、ドラゴンズ・落合監督の奥さまこと、おっかぁ~ の母校です。
遠方に住み、なかなか墓参りにも行けない状態ですが、ここのお寺のいいところは、戸別の墓ではなく、みんなまとめて仲良しの「納骨堂」方式だと言うことです。

だからいつ行っても、堂内は綺麗に掃き清められ、線香が焚かれ、溢れるほどに花が飾られている。
隣りが幼稚園なので、可愛らしい子どもたちの声と、本堂での読経もよく響く、誠にありがたい環境なのです。
このまま少子高齢化が進めば、いずれ墓守もできない家も出てくるでしょう。
実際、わが家の隣りの墓は、子孫が音信不通で、何年も無縁仏状態です。
こうなると戸別の墓よりは、やはり納骨堂の方がいいですね。

飯田女子高校は、ドラゴンズ・落合監督の奥さまこと、おっかぁ~ の母校です。
遠方に住み、なかなか墓参りにも行けない状態ですが、ここのお寺のいいところは、戸別の墓ではなく、みんなまとめて仲良しの「納骨堂」方式だと言うことです。

だからいつ行っても、堂内は綺麗に掃き清められ、線香が焚かれ、溢れるほどに花が飾られている。
隣りが幼稚園なので、可愛らしい子どもたちの声と、本堂での読経もよく響く、誠にありがたい環境なのです。
このまま少子高齢化が進めば、いずれ墓守もできない家も出てくるでしょう。
実際、わが家の隣りの墓は、子孫が音信不通で、何年も無縁仏状態です。
こうなると戸別の墓よりは、やはり納骨堂の方がいいですね。

Posted by mahora at
13:25
│Comments(0)