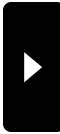2007年09月29日
アンゴラ料理その2
2回目のアンゴラ料理教室。
といっても今回で終わりです。
本日のメニューは、肉や野菜・インゲン豆をトマトソースで煮たフェジュアダ(ブラジル料理のフェジョンに近い)
ティラピアという、鯉と鯛を足して2で割ったような淡水魚に、ニンニクなどの香辛料を添えて焼くマンディオカ。
インディカ米の炊き込みピラフ
バナナの一種のプランティンを油で素揚げにして、シナモンシュガーでデコしたバナナ揚げだった。
魚のティラピアは大型の淡水魚で、川魚特有の生臭さがあったけど、香辛料でかなりカバーしていた。
白身の淡白な味で見た目より美味しいけど、小骨が多いのが難点です。
フェジュアダは、インゲン豆と各種野菜がマッチした、豆入りヘルシー野菜スープといったところか…
意外だったのが、プランティン(バナナ揚げ)だった。
近辺では手に入らないので、ネットで購入したらしいけど、中身は黄色というよりオレンジ色がかっていた。
生で食べても甘くなく、アンゴラでは茹でて小麦粉と練ったり、油揚げにして食べるとのこと。
茹でても甘くはならないけど、油で揚げると不思議と甘くなる。
どういう化学変化をして、甘味が引き出されるのか?…興味がわいた。
お菓子以外では砂糖は使わず、醤油や味噌などの発酵食品が存在しないためか、味付けの基本はすべて塩のみだった。
計量も、調理時間もアバウトで、適当に! 適当に! OK! OK! の連続で、それでもちゃんとできあがる、楽しい料理教室だった。
といっても今回で終わりです。
本日のメニューは、肉や野菜・インゲン豆をトマトソースで煮たフェジュアダ(ブラジル料理のフェジョンに近い)
ティラピアという、鯉と鯛を足して2で割ったような淡水魚に、ニンニクなどの香辛料を添えて焼くマンディオカ。
インディカ米の炊き込みピラフ
バナナの一種のプランティンを油で素揚げにして、シナモンシュガーでデコしたバナナ揚げだった。
魚のティラピアは大型の淡水魚で、川魚特有の生臭さがあったけど、香辛料でかなりカバーしていた。
白身の淡白な味で見た目より美味しいけど、小骨が多いのが難点です。
フェジュアダは、インゲン豆と各種野菜がマッチした、豆入りヘルシー野菜スープといったところか…
意外だったのが、プランティン(バナナ揚げ)だった。
近辺では手に入らないので、ネットで購入したらしいけど、中身は黄色というよりオレンジ色がかっていた。
生で食べても甘くなく、アンゴラでは茹でて小麦粉と練ったり、油揚げにして食べるとのこと。
茹でても甘くはならないけど、油で揚げると不思議と甘くなる。
どういう化学変化をして、甘味が引き出されるのか?…興味がわいた。
お菓子以外では砂糖は使わず、醤油や味噌などの発酵食品が存在しないためか、味付けの基本はすべて塩のみだった。
計量も、調理時間もアバウトで、適当に! 適当に! OK! OK! の連続で、それでもちゃんとできあがる、楽しい料理教室だった。

Posted by mahora at
15:51
│Comments(0)
2007年09月28日
鉄板病
番組プロデューサー・大学講師・デザイナーなど、多くの肩書きを持つ、おちまさとの「鉄板病」(NHK出版)
タイトルに惹かれて買いましたが、★4つでお勧めします。
元来はギャンブル用語で、荒れることなく走る前から勝者が決まっている手堅いレースを指す、鉄板レースから引用しています。
今、現代日本にこの鉄板的思考=鉄板病の人間が増殖し、社会全体を生きづらく、そしてつまらないものにしていると、指摘しています。
そして、この鉄板病に罹らないためには、自分の立ち位置を、常にグレーゾーンに置け! とアドバイスしています。
要は大衆とは逆の方向へ行け! と言うことか?
※こうして、深く検証もせず、結論を導きだすのも「鉄板病」の症状としています。
「常に正解ゾーンにいたい」「損はしたくない」「いつでも多数派にいたい」「人の考えを鵜呑みにする」など、様々な鉄板病症状が書かれていますが、鉄板病罹患度をチェックする13項目があります。
チェック項目が多い人ほど、重症な鉄板病です。お試しあれ!
□ 話題のダイエットDVDは早速購入した
□ 選挙で泡沫候補には投票しない
□ 本を買うとき、上から二番目をとる
□ レストランを決めるとき、グルメサイトのレビューを読む
□ 結論だけをズバリ言うようにしている
□ 会議を混乱させる発言をする奴はダメだと思う
□ チーズフォンデュはおしゃれだと思う
□ 『鈍感力』と聞いて、これこそ人生を生き抜くのに必要だ! と思った
□ 「どんだけ~」と日常的に使っている
□ 全米ナンバーワン映画は見逃せない
□ プレゼンには、基本パワーポイントを使う
□ やっぱり民主党だよ、と思っていた
□ いつも同僚のミスに足を引っ張られる
タイトルに惹かれて買いましたが、★4つでお勧めします。
元来はギャンブル用語で、荒れることなく走る前から勝者が決まっている手堅いレースを指す、鉄板レースから引用しています。
今、現代日本にこの鉄板的思考=鉄板病の人間が増殖し、社会全体を生きづらく、そしてつまらないものにしていると、指摘しています。
そして、この鉄板病に罹らないためには、自分の立ち位置を、常にグレーゾーンに置け! とアドバイスしています。
要は大衆とは逆の方向へ行け! と言うことか?
※こうして、深く検証もせず、結論を導きだすのも「鉄板病」の症状としています。
「常に正解ゾーンにいたい」「損はしたくない」「いつでも多数派にいたい」「人の考えを鵜呑みにする」など、様々な鉄板病症状が書かれていますが、鉄板病罹患度をチェックする13項目があります。
チェック項目が多い人ほど、重症な鉄板病です。お試しあれ!
□ 話題のダイエットDVDは早速購入した
□ 選挙で泡沫候補には投票しない
□ 本を買うとき、上から二番目をとる
□ レストランを決めるとき、グルメサイトのレビューを読む
□ 結論だけをズバリ言うようにしている
□ 会議を混乱させる発言をする奴はダメだと思う
□ チーズフォンデュはおしゃれだと思う
□ 『鈍感力』と聞いて、これこそ人生を生き抜くのに必要だ! と思った
□ 「どんだけ~」と日常的に使っている
□ 全米ナンバーワン映画は見逃せない
□ プレゼンには、基本パワーポイントを使う
□ やっぱり民主党だよ、と思っていた
□ いつも同僚のミスに足を引っ張られる

Posted by mahora at
16:43
│Comments(0)
2007年09月27日
トキワ荘プロジェクト
昨日の毎日新聞にNPO法人コトバノアトリエがプロデュースする、トキワ荘プロジェクトの紹介記事が載っていた。
手塚治虫、藤子不二雄、赤塚不二夫らを生んだアパート・トキワ荘にちなんで、地方から漫画家を志して上京する若者に、民家を借上げて格安で貸したり、出版社との橋渡しなどでデビューを後押しするらしい。
入居者は、原則1年で芽が出なければ、退去しなければならないが、孤独と不安に耐えながら夢を追い続けるよりも、同じ屋根の下で多くの仲間たちに支えられながら、切磋琢磨して目標の実現に励む。
コトバノアトリエのホームページには、「若者が好きなことを仕事にできる社会環境の創造を目指して活動する非営利団体です。作家、ライター、漫画家などのクリエイティブな仕事に就きたいニート・ひきこもり・フリーターの若者を育成・支援しています」とある。
代表の山本繁は29歳で、慶應大学を出た時は就職氷河期で、いわゆるロストジェネレーションとか、精神科医の香山リカが名づけた貧乏くじ世代にあたる。
「東京の高い地価が僕らの世代から機会を奪っている」と言うように、この世代は昨今の景気回復(?)で、その存在すら忘れ去られている感じです。
時代の巡り合せで、就職活動と言う土俵にさえ上がれなかった若者と、その彼らを支える同じ世代の若者たち…
夢に賭けようと、再び立ち上がった若者たちの前途が、明るく輝くことを祈るばかりです。
でも、よく考えれば、これって本来、国家がやるべきことだよね。
そう言えば最近プッツンした、かの総理大臣も就任したころには「再チャレンジ! 再チャレンジ!」って盛んに言っていたけど…
ぜひ、総理大臣に再チャレンジして、お手本を示してください!
手塚治虫、藤子不二雄、赤塚不二夫らを生んだアパート・トキワ荘にちなんで、地方から漫画家を志して上京する若者に、民家を借上げて格安で貸したり、出版社との橋渡しなどでデビューを後押しするらしい。
入居者は、原則1年で芽が出なければ、退去しなければならないが、孤独と不安に耐えながら夢を追い続けるよりも、同じ屋根の下で多くの仲間たちに支えられながら、切磋琢磨して目標の実現に励む。
コトバノアトリエのホームページには、「若者が好きなことを仕事にできる社会環境の創造を目指して活動する非営利団体です。作家、ライター、漫画家などのクリエイティブな仕事に就きたいニート・ひきこもり・フリーターの若者を育成・支援しています」とある。
代表の山本繁は29歳で、慶應大学を出た時は就職氷河期で、いわゆるロストジェネレーションとか、精神科医の香山リカが名づけた貧乏くじ世代にあたる。
「東京の高い地価が僕らの世代から機会を奪っている」と言うように、この世代は昨今の景気回復(?)で、その存在すら忘れ去られている感じです。
時代の巡り合せで、就職活動と言う土俵にさえ上がれなかった若者と、その彼らを支える同じ世代の若者たち…
夢に賭けようと、再び立ち上がった若者たちの前途が、明るく輝くことを祈るばかりです。
でも、よく考えれば、これって本来、国家がやるべきことだよね。
そう言えば最近プッツンした、かの総理大臣も就任したころには「再チャレンジ! 再チャレンジ!」って盛んに言っていたけど…
ぜひ、総理大臣に再チャレンジして、お手本を示してください!

Posted by mahora at
16:42
│Comments(0)
2007年09月25日
五行歌って…
五行歌といって、俳句や短歌のような定型詩の形を採らず、一行をひと息で読める長さとして、全体を五行でおさめるという規制以外に、一切の制約を外した詩歌がある。
草壁焔太(くさかべえんた)と言う人が創始者で、全国的にも多くの愛好者があり、信州でも小諸と長野に支部があるらしい。
友人がこの会に入っていて、時々入選して、機関誌にも掲載されている。
学生時代から詩を書くことが好きだったけど、俳句や短歌などでは、細かい制約があり、心象風景を思うように表現するには、少し窮屈だったけど、この五行歌はピタッ! とツボにはまるものがあったとのこと。
月に1度の勉強会でも、それぞれが思う作品を発表しあうだけで、お互い批評し合ったり、先生が添削指導することはなく、自由でのびのびと表現できるのが、なんとも心地よいらしい。
で、私もまねごとを…
筋肉痛
年に一度の
稲刈りで
日ごろの怠慢
身にしみる


草壁焔太(くさかべえんた)と言う人が創始者で、全国的にも多くの愛好者があり、信州でも小諸と長野に支部があるらしい。
友人がこの会に入っていて、時々入選して、機関誌にも掲載されている。
学生時代から詩を書くことが好きだったけど、俳句や短歌などでは、細かい制約があり、心象風景を思うように表現するには、少し窮屈だったけど、この五行歌はピタッ! とツボにはまるものがあったとのこと。
月に1度の勉強会でも、それぞれが思う作品を発表しあうだけで、お互い批評し合ったり、先生が添削指導することはなく、自由でのびのびと表現できるのが、なんとも心地よいらしい。
で、私もまねごとを…
筋肉痛
年に一度の
稲刈りで
日ごろの怠慢
身にしみる


Posted by mahora at
16:00
│Comments(0)
2007年09月22日
知る人ぞ知るワイン
秋の彼岸だというのに、いっこうに収まりそうもない暑さです。
人肌恋しい秋はどこへやら…という感じですが、今年も新酒のワインの注文がきて、季節の移ろいを感じています。
実はワインの中にブラッシュといって、赤ワイン用品種を白ワインの製法で醸造したものがあるということを、教えていただいた。
今回は巨峰のブラッシュで、極端に数が少なく、ワイナリーでも、あまりおおっぴらには宣伝できない、知る人ぞ知るワインとのこと。
今年はこのブラッシュを注文してみることにした。
ああ! 早く、ひんやり秋風に吹かれ、まん丸お月さんを眺めながら、ワインを楽しむ季節が来ないかなぁ…!
人肌恋しい秋はどこへやら…という感じですが、今年も新酒のワインの注文がきて、季節の移ろいを感じています。
実はワインの中にブラッシュといって、赤ワイン用品種を白ワインの製法で醸造したものがあるということを、教えていただいた。
今回は巨峰のブラッシュで、極端に数が少なく、ワイナリーでも、あまりおおっぴらには宣伝できない、知る人ぞ知るワインとのこと。
今年はこのブラッシュを注文してみることにした。
ああ! 早く、ひんやり秋風に吹かれ、まん丸お月さんを眺めながら、ワインを楽しむ季節が来ないかなぁ…!

Posted by mahora at
13:57
│Comments(0)
2007年09月21日
悲しみのキャンパス 石田徹也
今週のAERAで、夭折の天才アーティスト・石田徹也が特集されている。
この異才画家のことを初めて知った。
公式ホームページが開設されているので、その高い精神性の衝撃的な作品は、そちらで閲覧してください。
http://www.tetsuyaishida.jp/
一昨年の5月に不慮の事故により、31歳と言う若さでこの世を去ってしまったが、生前、彼の才能を見抜き、支えてきた人たちの労力で、その作品が陽の目を見るようになった。
昨年9月のNHK教育TVの「新日曜美術館」で放送されたことから、広く知られるようになり、遺稿集もAmazonで売上1位になった。
アートは観る人、それぞれ個人の感じ方でいいわけですが、この人の絵を鑑賞するには生半可な気持ちでは、観られないなぁ…と思った。
やはりそれなりの覚悟がいる。
現代の金銭万能・効率優先の社会の中にどっぶり浸かり、日々流されるだけの主体性のない生き方をしている人は、強烈な一撃を喰らうと思う。
記事の中では、美大を卒業して極貧の中で創作活動に励む石田に、両親が援助を申し出ても「自分がだめになるから」と断り、交際していた女性とも「幸せすぎて絵が描けないから」と別れてしまった…と言うエピソードが紹介されていた。
ウーン!
この過剰な競争社会の中で、隙あらば少しでも出し抜こうと、虎視眈々と狙っている輩の多い中で、ここまでストイックに、自身を追い詰めて創作活動をしていた若者がいたなんて……
実際の作品はかなり巨大で、見る者すべてを圧倒するらしい。
ぜひ実物を、観てみたいと強く思った。
この異才画家のことを初めて知った。
公式ホームページが開設されているので、その高い精神性の衝撃的な作品は、そちらで閲覧してください。
http://www.tetsuyaishida.jp/
一昨年の5月に不慮の事故により、31歳と言う若さでこの世を去ってしまったが、生前、彼の才能を見抜き、支えてきた人たちの労力で、その作品が陽の目を見るようになった。
昨年9月のNHK教育TVの「新日曜美術館」で放送されたことから、広く知られるようになり、遺稿集もAmazonで売上1位になった。
アートは観る人、それぞれ個人の感じ方でいいわけですが、この人の絵を鑑賞するには生半可な気持ちでは、観られないなぁ…と思った。
やはりそれなりの覚悟がいる。
現代の金銭万能・効率優先の社会の中にどっぶり浸かり、日々流されるだけの主体性のない生き方をしている人は、強烈な一撃を喰らうと思う。
記事の中では、美大を卒業して極貧の中で創作活動に励む石田に、両親が援助を申し出ても「自分がだめになるから」と断り、交際していた女性とも「幸せすぎて絵が描けないから」と別れてしまった…と言うエピソードが紹介されていた。
ウーン!
この過剰な競争社会の中で、隙あらば少しでも出し抜こうと、虎視眈々と狙っている輩の多い中で、ここまでストイックに、自身を追い詰めて創作活動をしていた若者がいたなんて……
実際の作品はかなり巨大で、見る者すべてを圧倒するらしい。
ぜひ実物を、観てみたいと強く思った。

Posted by mahora at
16:47
│Comments(0)
2007年09月20日
青と赤の花回廊
須坂長野東インターから、須坂市栃倉地籍に延びるフラワーロードには、真っ赤なサルビアと、真っ青なヘブンリーブルーが1キロ近くに渡って見事に咲いていて、さしずめ花回廊といった感じで、ドライブしていても爽快な気分になる。
ヘブンリーブルーは西洋朝顔の一種で、別名・天上の青という。
その冴えた目の覚めるような、ビビッドブルーと、旺盛な繁殖力が人気を呼んでいるとか。
豪商の館・田中本家にも、このヘブンリーブルーの見事な棚がある。
朝顔と言うと真夏のイメージだけど、このヘブンリーブルーは8月下旬から9月が最盛期とのこと。
あまりの見事さに、車を止めて、デジカメで切り取ってみました。
このビューポイントを提供してくださる、地元の皆さまに感謝! 感謝です!
ヘブンリーブルーは西洋朝顔の一種で、別名・天上の青という。
その冴えた目の覚めるような、ビビッドブルーと、旺盛な繁殖力が人気を呼んでいるとか。
豪商の館・田中本家にも、このヘブンリーブルーの見事な棚がある。
朝顔と言うと真夏のイメージだけど、このヘブンリーブルーは8月下旬から9月が最盛期とのこと。
あまりの見事さに、車を止めて、デジカメで切り取ってみました。
このビューポイントを提供してくださる、地元の皆さまに感謝! 感謝です!

Posted by mahora at
16:18
│Comments(0)
2007年09月19日
土曜日はイタリアン
16日は黒姫高原の秋風に揺れるコスモスを堪能し、しばし暑さを忘れることができた。
そして、飯山の友人から、木島平村に土曜日はイタリアンという、パスタの美味しいお店があるから、そこでお昼を食べよう! いうことになり車を走らせた。


ここは友人の娘さんが、中学生の時の美術の先生が、教職を辞してまで開店したお店で、あのイチロー選手や、コピーライターの糸井重里など、チョー有名人も数多く来店しているとのこと……
ミーハーなオバサンたちは、こういう要素にめっぽう弱い!
行けども行けども山また山の、曲がりくねった道を、右へ左へとハンドルを切りながら、愛車のマーチを走らせたけど、北信濃のごくありふれた町並みで、こんな寒村に(村民の皆さま、ゴメンナサイ!)、大リーガーのイチローがぁ~?…と、半信半疑だった。
ところが、連休ということを差し引いても、すごい人たちで、午後2時近くという時間帯にもかかわらず、9組・2時間待ちと問答無用の宣告をされてしまい、やむなくあきらめた。
あまりにガッカリで、概観の写真を撮ってくるのも忘れてしまったぁ~!
長野の友人も、誰に聞いてもあそこは美味しい! との評判らしい。
今度は開店の1時間くらい前に並んでみよう! ということで話しがまとまった。
糸井さんのほぼ日刊イトイ新聞に、詳しく掲載されています。
http://www.1101.com/dressing/restaurant.html
どなたか、食されたことのある方は、教えてくださいね。

そして、飯山の友人から、木島平村に土曜日はイタリアンという、パスタの美味しいお店があるから、そこでお昼を食べよう! いうことになり車を走らせた。



ここは友人の娘さんが、中学生の時の美術の先生が、教職を辞してまで開店したお店で、あのイチロー選手や、コピーライターの糸井重里など、チョー有名人も数多く来店しているとのこと……

ミーハーなオバサンたちは、こういう要素にめっぽう弱い!

行けども行けども山また山の、曲がりくねった道を、右へ左へとハンドルを切りながら、愛車のマーチを走らせたけど、北信濃のごくありふれた町並みで、こんな寒村に(村民の皆さま、ゴメンナサイ!)、大リーガーのイチローがぁ~?…と、半信半疑だった。

ところが、連休ということを差し引いても、すごい人たちで、午後2時近くという時間帯にもかかわらず、9組・2時間待ちと問答無用の宣告をされてしまい、やむなくあきらめた。

あまりにガッカリで、概観の写真を撮ってくるのも忘れてしまったぁ~!

長野の友人も、誰に聞いてもあそこは美味しい! との評判らしい。
今度は開店の1時間くらい前に並んでみよう! ということで話しがまとまった。
糸井さんのほぼ日刊イトイ新聞に、詳しく掲載されています。
http://www.1101.com/dressing/restaurant.html
どなたか、食されたことのある方は、教えてくださいね。

Posted by mahora at
17:00
│Comments(0)
2007年09月18日
奇跡の旅
学生時代の友人2人と、菅平峰の原高原へ旅してきた。
私たちの年代は、親の介護・子どもの自立・自身の更年期症状など、さまざまな問題を抱えている、三重苦の世代です。
だから、1年に1回はこうして時間を作っては、日ごろのストレスを発散させることにしている。
題して「ヘレンケラー・奇跡の旅」といっている。
ただし、オバサンは3人以上集まると、その存在自体が脅威となるので、どんなに集まっても4人までと言うメンバー制限をしている。
宿泊したペンションで、ニュージーランド産のバニラアイスに、キャラメルソースを絡めたデザートをいただいた。
ミントとナスタチュームの花が添えられていて、味も見た目も美しく、雑事に追われる主婦には、それだけで満足できるものだった。
オーナーさんから10月21日(日)に行われる「雲の上のフェスタ&バザール」のチラシをいただいた。
午後の1時から、秋のお菓子パーティーと言うイベントがあって、峰の原の各ペンション自慢のスウィーツが、食べられるとのこと。
800円でお菓子5品とコーヒーまたは紅茶が付くらしい。
秋の高原で、手作りスウィーツ三昧を楽しみたい方は、ぜひ、出かけて下さい。
私たちの年代は、親の介護・子どもの自立・自身の更年期症状など、さまざまな問題を抱えている、三重苦の世代です。
だから、1年に1回はこうして時間を作っては、日ごろのストレスを発散させることにしている。
題して「ヘレンケラー・奇跡の旅」といっている。
ただし、オバサンは3人以上集まると、その存在自体が脅威となるので、どんなに集まっても4人までと言うメンバー制限をしている。
宿泊したペンションで、ニュージーランド産のバニラアイスに、キャラメルソースを絡めたデザートをいただいた。
ミントとナスタチュームの花が添えられていて、味も見た目も美しく、雑事に追われる主婦には、それだけで満足できるものだった。
オーナーさんから10月21日(日)に行われる「雲の上のフェスタ&バザール」のチラシをいただいた。
午後の1時から、秋のお菓子パーティーと言うイベントがあって、峰の原の各ペンション自慢のスウィーツが、食べられるとのこと。
800円でお菓子5品とコーヒーまたは紅茶が付くらしい。
秋の高原で、手作りスウィーツ三昧を楽しみたい方は、ぜひ、出かけて下さい。

Posted by mahora at
13:11
│Comments(0)
2007年09月17日
ええ年寄りになりなはれ
敬老の日なんですね。
数年前からハッピーマンデーの「9月の第3月曜日」に変わったわけです。
月曜日を祝日にし、連休を作ることで、消費拡大で景気回復を…という目論見ですが、そういった、経済至上主義の不純な動機でいいのかなぁ……?
老人予備群ですので、自分もこうなりたいと言う、願望も含めて…
山口市瑠璃光寺で見つけた、含蓄ある文言です!
ぼけたらあかん 長生きしなはれ
泣きごとに 人の陰口 グチ言わず 他人のことはほめなはれ
いつでもアホでおりなはれ
若い者には花もたせ 一歩下がっておることだ
いずれお世話になる身なら
いつも感謝を忘れずに どんな時でも へぇおおきに
お金の欲は捨てなはれ 生きているうちにばらまいて 山ほど徳を積みなはれ
昔のことは忘れなはれ
自慢ばなしに わしらの時はなんて 鼻持ちならぬ 忌み言葉
我が子に孫に世間さま どなたからでも慕われる ええ年寄りになりなはれ
ボケたらあかん
そのために 何か一つの趣味もって せいぜい長生きしなはれや
数年前からハッピーマンデーの「9月の第3月曜日」に変わったわけです。
月曜日を祝日にし、連休を作ることで、消費拡大で景気回復を…という目論見ですが、そういった、経済至上主義の不純な動機でいいのかなぁ……?
老人予備群ですので、自分もこうなりたいと言う、願望も含めて…
山口市瑠璃光寺で見つけた、含蓄ある文言です!
ぼけたらあかん 長生きしなはれ
泣きごとに 人の陰口 グチ言わず 他人のことはほめなはれ
いつでもアホでおりなはれ
若い者には花もたせ 一歩下がっておることだ
いずれお世話になる身なら
いつも感謝を忘れずに どんな時でも へぇおおきに
お金の欲は捨てなはれ 生きているうちにばらまいて 山ほど徳を積みなはれ
昔のことは忘れなはれ
自慢ばなしに わしらの時はなんて 鼻持ちならぬ 忌み言葉
我が子に孫に世間さま どなたからでも慕われる ええ年寄りになりなはれ
ボケたらあかん
そのために 何か一つの趣味もって せいぜい長生きしなはれや

Posted by mahora at
14:56
│Comments(0)
2007年09月14日
明日、本番です!
明日は近くの小学校の運動会です。


連日の猛練習で、先生が一生懸命指導している掛け声が、マイクを通してよく聞こえてきます。
晴天を祈るばかりです!


ここの小学校はあの「総合学習」で、全国的に名を知られた学校で、運動会はその成果を発表する絶好の機会です。
だから、他の学校の運動会とは比べ物にならないくらい、熱が入り、ボルテージも上がります。
……と言うのも、すでに過去の話らしい。
この「総合学習」と言う、かなりアバウトな指導方法が、教育界の遺物となりつつあるからです。
我が子の晴れ姿をカメラにおさめようと、競技そっちのけの保護者と、それを注意指導する教師のバトルは、運動会ではもはや、当たり前の光景らしい。
この国は総理大臣初め、みんな自分大事、自己中心の人たちばかりになってしまったんだね。




連日の猛練習で、先生が一生懸命指導している掛け声が、マイクを通してよく聞こえてきます。
晴天を祈るばかりです!



ここの小学校はあの「総合学習」で、全国的に名を知られた学校で、運動会はその成果を発表する絶好の機会です。
だから、他の学校の運動会とは比べ物にならないくらい、熱が入り、ボルテージも上がります。
……と言うのも、すでに過去の話らしい。
この「総合学習」と言う、かなりアバウトな指導方法が、教育界の遺物となりつつあるからです。

我が子の晴れ姿をカメラにおさめようと、競技そっちのけの保護者と、それを注意指導する教師のバトルは、運動会ではもはや、当たり前の光景らしい。
この国は総理大臣初め、みんな自分大事、自己中心の人たちばかりになってしまったんだね。


Posted by mahora at
13:36
│Comments(0)
2007年09月13日
実はスゴイ人なんですよ!
当市の生涯学習センターのロビーに、刻字作品が飾られている。
先日の料理教室の時に、寄贈者名を見たら「宮澤梅径」先生だった。
実はこの方、ご近所の酒屋さんのご主人で、刻字作家としてはかなり有名な方です。
毎日書道展・書道芸術院で審査員などもされ、また、松本のNHK文化センターの講師や、地元でも教室を開き、多くのお弟子さんをかかえている。
市役所のロビーにも迫力ある大作「龍魔風神」を寄贈され、常設展示されています。
刻字は一般書道の基本を踏まえながら、斬新な書体とセンスで描いたものを、桂の木などに写して彫刻し、金粉やアクリル絵の具などで、色付けしていくらしい。
畳1枚分くらいある大作となると、かなりの根気と集中力、そして体力を要する作業です。
時々、個展も開催していますが、大型作品となるとそれなりの価格で、すぐには手が出せません。
ただ、画仙紙で掛け軸スタイルの書では、床の間でないとしっくりきませんが、刻字は和室洋室どちらにも合うので、需要としては高いようです。
高遠の名酒「黒松仙醸」のラベル文字も、梅径先生の書によるものです。
お店では物腰やわらかい優しそうな、ごくごく普通の酒屋のご主人なんだけど、実は郷土が誇る凄い文化人なんです。
好きだなぁ! こういう人…
こういう人…
先日の料理教室の時に、寄贈者名を見たら「宮澤梅径」先生だった。
実はこの方、ご近所の酒屋さんのご主人で、刻字作家としてはかなり有名な方です。
毎日書道展・書道芸術院で審査員などもされ、また、松本のNHK文化センターの講師や、地元でも教室を開き、多くのお弟子さんをかかえている。
市役所のロビーにも迫力ある大作「龍魔風神」を寄贈され、常設展示されています。
刻字は一般書道の基本を踏まえながら、斬新な書体とセンスで描いたものを、桂の木などに写して彫刻し、金粉やアクリル絵の具などで、色付けしていくらしい。
畳1枚分くらいある大作となると、かなりの根気と集中力、そして体力を要する作業です。
時々、個展も開催していますが、大型作品となるとそれなりの価格で、すぐには手が出せません。
ただ、画仙紙で掛け軸スタイルの書では、床の間でないとしっくりきませんが、刻字は和室洋室どちらにも合うので、需要としては高いようです。
高遠の名酒「黒松仙醸」のラベル文字も、梅径先生の書によるものです。

お店では物腰やわらかい優しそうな、ごくごく普通の酒屋のご主人なんだけど、実は郷土が誇る凄い文化人なんです。
好きだなぁ!
 こういう人…
こういう人…
Posted by mahora at
14:27
│Comments(0)
2007年09月12日
女王陛下の憂鬱
ダイアナ元妃の事故死から、10年という歳月が流れたけど、昨夜の例会は英仏伊合作の「THE QUEEN 」だった。
突然の予期せぬ事態に直面したロイヤルファミリー、とりわけエリザベス女王が苦悩しながらも、連合王国君主としての威厳を保つため下した決断を、中心に描かれていました。
実話のうえ、王室というある種、禁断の世界を描くことは、一歩間違えれば、単なる覗き見趣味的な、興味本位の安っぽい作品になってしまう。
スタッフもかなり綿密な調査取材をし、客観的裏づけの元に、事実を忠実に再現していることはよく伝わってきた。
でも、すみませんが所詮、別世界の話かなぁ…って思いました。
女王陛下と言えども、普通の人間ですよ、姑ですよ、母親ですよ。
明るく自由奔放で、国民から絶大な人気の嫁が、気に入らないこともあるでしょう。
妻も子どももありながら、平気で愛人を作る息子に、ふがいなさも感じるでしょう。
泣いたり、怒ったり、感情的になることもありますよ。
でも、一歩宮殿の外に出れば、常に女王としての品位と威厳を保ち、国民の畏敬と敬愛の対象となるため、どれだけ苦悩しているのか…と言ったことを描きたかったのだろうと思う。
女王を演じたヘレン・ミレン(アカデミー賞最優秀主演女優賞)がそっくりを超えて、女王そのものになりきった風格ある演技で、作品の質を高めていました。
それにしても、チャールズ皇太子はじめ、フィリップ殿下といい、王室の男どもは役に立たないねぇ…
一生、鹿撃ちしてて下さい!
突然の予期せぬ事態に直面したロイヤルファミリー、とりわけエリザベス女王が苦悩しながらも、連合王国君主としての威厳を保つため下した決断を、中心に描かれていました。
実話のうえ、王室というある種、禁断の世界を描くことは、一歩間違えれば、単なる覗き見趣味的な、興味本位の安っぽい作品になってしまう。
スタッフもかなり綿密な調査取材をし、客観的裏づけの元に、事実を忠実に再現していることはよく伝わってきた。
でも、すみませんが所詮、別世界の話かなぁ…って思いました。
女王陛下と言えども、普通の人間ですよ、姑ですよ、母親ですよ。
明るく自由奔放で、国民から絶大な人気の嫁が、気に入らないこともあるでしょう。
妻も子どももありながら、平気で愛人を作る息子に、ふがいなさも感じるでしょう。
泣いたり、怒ったり、感情的になることもありますよ。
でも、一歩宮殿の外に出れば、常に女王としての品位と威厳を保ち、国民の畏敬と敬愛の対象となるため、どれだけ苦悩しているのか…と言ったことを描きたかったのだろうと思う。
女王を演じたヘレン・ミレン(アカデミー賞最優秀主演女優賞)がそっくりを超えて、女王そのものになりきった風格ある演技で、作品の質を高めていました。
それにしても、チャールズ皇太子はじめ、フィリップ殿下といい、王室の男どもは役に立たないねぇ…
一生、鹿撃ちしてて下さい!

Posted by mahora at
12:08
│Comments(0)
2007年09月11日
その名は笑い栗
夏の最後尾と、秋の最前列にいるような陽気ですね。
食欲の秋に、近所の酒屋さんで「笑い栗」なるものを発見しましたっ!
あのカネボウ(産業再生機構の元で、今はKracie〈クラシエ〉と社名を変更したらしいです)のヒット商品、「甘栗むいちゃいました」の皮付きヴァージョンです。
皮付きならふつうの天津甘栗だってぇ~?
いえいえ! 「栗がパックリ笑ってる!」のコピーどおり、底がパックリと割れていて、爪を立てて割れ目を入れることも、手が汚れることもなく、美味しく食べられるのですよ。
おまけに、パカッ!っと底が割れた栗の表情が、ニッコリ微笑んでいるようにも、人をバカにして笑っているようにも見え、なんとも愉快で、遊び心があります。
ネーミングの「笑い栗」にも含みがあり、商品状態ダイレクトの「甘栗むいちゃいました」より、断然いいですよね。
やっぱりこうした加工食品は、ネーミングでも美味しさを感じさせないと……
今は、考えるより感じる時代らしいですからね。
そう言えば、カネボウの新しい社名 Kracie〈クラシエ〉も「暮らしへ」から、採っているとか…
良くいえば、事業内容をシンプルにして雄弁に物語り、悪くいえば、チョー安易ですっ!

食欲の秋に、近所の酒屋さんで「笑い栗」なるものを発見しましたっ!

あのカネボウ(産業再生機構の元で、今はKracie〈クラシエ〉と社名を変更したらしいです)のヒット商品、「甘栗むいちゃいました」の皮付きヴァージョンです。
皮付きならふつうの天津甘栗だってぇ~?

いえいえ! 「栗がパックリ笑ってる!」のコピーどおり、底がパックリと割れていて、爪を立てて割れ目を入れることも、手が汚れることもなく、美味しく食べられるのですよ。
おまけに、パカッ!っと底が割れた栗の表情が、ニッコリ微笑んでいるようにも、人をバカにして笑っているようにも見え、なんとも愉快で、遊び心があります。

ネーミングの「笑い栗」にも含みがあり、商品状態ダイレクトの「甘栗むいちゃいました」より、断然いいですよね。
やっぱりこうした加工食品は、ネーミングでも美味しさを感じさせないと……
今は、考えるより感じる時代らしいですからね。

そう言えば、カネボウの新しい社名 Kracie〈クラシエ〉も「暮らしへ」から、採っているとか…
良くいえば、事業内容をシンプルにして雄弁に物語り、悪くいえば、チョー安易ですっ!


Posted by mahora at
16:18
│Comments(0)
2007年09月10日
アンゴラ料理その1
8日に生涯学習センター主催の「アンゴラ料理教室」に参加した。
駒ヶ根市のJICAとセンターがタッグを組んでの、世界の家庭料理シリーズのひとつです。
講師はイギリス国籍のカルロス・オリベイラさんで、日本語3割、英語7割状態だったけど、奥さんが日本人で、受講者の中にもバイリンガルな人もいて、安心して鍋・釜・包丁ふりまわし? 身振り手振りで、どうにか3品を仕上げた。
鶏肉と野菜をトマトソースで煮込むムアンバは、見た目はシチューなんだけど、最大の特徴は仕上げに、ピーナツバターのSkippy缶420gを入れることです。
Skippyは練りゴマのピーナツバージョンで、甘くないものと想像して下さい。
レシピを見たときは、香ばしさを出すための、隠し味程度かと思っていたら、1缶投入と聞いて一同驚いたけど、これでシチューが、アンゴラ版濃い目の味噌汁になった。
ムアンバに添えるジングンドと言う薬味には、唐辛子の何十倍も辛いハバネロと、ニンニク・玉葱のみじん切りをオリーブオイルに漬けたものをつかった。
強烈な辛さで、このままアフリカ大陸へ飛ばされるかと思ったっ!
多少デフォしています
フンジはキャッサバの粉を練って作る、お団子のようなもので主食代わりのものです。
特徴的な味はなく、触感もお餅というより、すいとんに近い感じだった。
アンゴラと言えば内戦と飢餓のイメージしかなかったけど、2002年に平和協定が結ばれたらしい。
やっと訪れた平穏な日々が、永遠に続くことを祈るばかりです。

駒ヶ根市のJICAとセンターがタッグを組んでの、世界の家庭料理シリーズのひとつです。
講師はイギリス国籍のカルロス・オリベイラさんで、日本語3割、英語7割状態だったけど、奥さんが日本人で、受講者の中にもバイリンガルな人もいて、安心して鍋・釜・包丁ふりまわし? 身振り手振りで、どうにか3品を仕上げた。
鶏肉と野菜をトマトソースで煮込むムアンバは、見た目はシチューなんだけど、最大の特徴は仕上げに、ピーナツバターのSkippy缶420gを入れることです。
Skippyは練りゴマのピーナツバージョンで、甘くないものと想像して下さい。
レシピを見たときは、香ばしさを出すための、隠し味程度かと思っていたら、1缶投入と聞いて一同驚いたけど、これでシチューが、アンゴラ版濃い目の味噌汁になった。
ムアンバに添えるジングンドと言う薬味には、唐辛子の何十倍も辛いハバネロと、ニンニク・玉葱のみじん切りをオリーブオイルに漬けたものをつかった。
強烈な辛さで、このままアフリカ大陸へ飛ばされるかと思ったっ!

多少デフォしています

フンジはキャッサバの粉を練って作る、お団子のようなもので主食代わりのものです。
特徴的な味はなく、触感もお餅というより、すいとんに近い感じだった。
アンゴラと言えば内戦と飢餓のイメージしかなかったけど、2002年に平和協定が結ばれたらしい。
やっと訪れた平穏な日々が、永遠に続くことを祈るばかりです。


Posted by mahora at
13:50
│Comments(0)
2007年09月08日
日本版「本の町」なるか
昨日、高遠から茅野へ抜ける杖突峠の道路沿いにある「高遠 本の家」と言う、古本屋へ行ってきた。
東京の古書店主6人が集まり、イギリスのヘイオンワイのような「本の町」を創ろう! と言う志を抱いて7月にオープンした。
高遠町長藤(オサフジ)栗田地籍にあり、旅籠だった古民家を借り、東京から古本を運び込んで陳列販売している。
リフォームはせず、黒光りする天井や帯戸など、旅籠らしい風情を残し、畳の上で寝転んだり、コーヒーなどの喫茶もあるので、静かに(前の道路を走る車の音がスゴイけど…)落ち着いて読むことができる、ブックカフェです。
そう! 空き家が目立つ過疎の古い町に、旅籠だった古民家に、そして古書と言う、この三重苦をうまく利用しているわけです。
メンバーには、ネット古書店の経営者にしてライターの、北尾トロさん(「裁判長!これで執行猶予は甘くないすか」「怪しいお仕事!」)など、その道では名の通った人がいるらしいです。
昨日は村上龍と、映画関係の本など2,000円ほど買い込んだ。
オープンして日が浅いので、傾向を探りながら内容を充実させていきたい、と言っていたけど、売れる本と売りたい本は違うところが、難しいだろうなぁ…と思う。
実は、このお店の道路を挟んだ、東隣の家が親戚で、昨日はそこに用があったのだが、なぜ、こんなひなびた町に来たのか…肝心なことを訊いてくるのを忘れたっ!
看板も控え目で、風景に溶け込んでいるので、注意していないと通り過ぎてしまいそうです。
東京の古書店主6人が集まり、イギリスのヘイオンワイのような「本の町」を創ろう! と言う志を抱いて7月にオープンした。
高遠町長藤(オサフジ)栗田地籍にあり、旅籠だった古民家を借り、東京から古本を運び込んで陳列販売している。
リフォームはせず、黒光りする天井や帯戸など、旅籠らしい風情を残し、畳の上で寝転んだり、コーヒーなどの喫茶もあるので、静かに(前の道路を走る車の音がスゴイけど…)落ち着いて読むことができる、ブックカフェです。
そう! 空き家が目立つ過疎の古い町に、旅籠だった古民家に、そして古書と言う、この三重苦をうまく利用しているわけです。
メンバーには、ネット古書店の経営者にしてライターの、北尾トロさん(「裁判長!これで執行猶予は甘くないすか」「怪しいお仕事!」)など、その道では名の通った人がいるらしいです。
昨日は村上龍と、映画関係の本など2,000円ほど買い込んだ。
オープンして日が浅いので、傾向を探りながら内容を充実させていきたい、と言っていたけど、売れる本と売りたい本は違うところが、難しいだろうなぁ…と思う。
実は、このお店の道路を挟んだ、東隣の家が親戚で、昨日はそこに用があったのだが、なぜ、こんなひなびた町に来たのか…肝心なことを訊いてくるのを忘れたっ!
看板も控え目で、風景に溶け込んでいるので、注意していないと通り過ぎてしまいそうです。

Posted by mahora at
14:52
│Comments(0)
2007年09月07日
羽ばたく
昨夜の台風も、当地では大したことなく過ぎ去り、ホッとしています。
皆さんの地域はどうでしたか?
昨夜、東京の兄から久しぶりに電話があった。
甥(兄の長男)が、10月から東京メトロへ転職することになり、今の運送会社を今月いっぱいで辞めることになったから…と話してくれた。


小さな時から電車が大好きで、鉄ちゃん系のところがあったけど、大学卒業後は鉄路ではなく、道路関連の仕事に就いていた。


すでに結婚して子どもが二人もいるので、転職するなら30歳前にすること、転職先が確定してから、辞表を出すことを約束させて、休日や有給を使って、転職活動をしていたらしい…
「未来をあきらめない!」は映画フラガールのコピーだったけど、こちらは「夢をあきらめない!」と言ったところか…
本人はだいぶ苦労して頑張ったらしく、幸運にも希望が叶い、とても喜んでいるらしい。
心から祝福してあげたい!


皆さんの地域はどうでしたか?
昨夜、東京の兄から久しぶりに電話があった。
甥(兄の長男)が、10月から東京メトロへ転職することになり、今の運送会社を今月いっぱいで辞めることになったから…と話してくれた。



小さな時から電車が大好きで、鉄ちゃん系のところがあったけど、大学卒業後は鉄路ではなく、道路関連の仕事に就いていた。



すでに結婚して子どもが二人もいるので、転職するなら30歳前にすること、転職先が確定してから、辞表を出すことを約束させて、休日や有給を使って、転職活動をしていたらしい…
「未来をあきらめない!」は映画フラガールのコピーだったけど、こちらは「夢をあきらめない!」と言ったところか…
本人はだいぶ苦労して頑張ったらしく、幸運にも希望が叶い、とても喜んでいるらしい。
心から祝福してあげたい!


Posted by mahora at
14:27
│Comments(0)
2007年09月06日
米の道を歩く
当市の民謡「伊那節」に
木曽へ木曽へとつけ出す米は 伊那や高遠の伊那や高遠の涙米
涙米とはそりゃ情けない 伊那や高遠の伊那や高遠の余り米
と言うのがある。
昔、お米の獲れなった木曽地方へ、伊那の米を馬の背に乗せ、権兵衛峠を越えて運んで行ったことを謡っている。
昨年の2月に権兵衛トンネルが開通して、木曽と伊那は通勤圏内になった。
毎年10月に当市では、往時を偲んで「米の道・権兵衛峠を歩こう」と言うイベントを開催している。
現在はほとんど使われていない、かつての峠道を歩くこのイベントに、県内外から300人以上の人たちが参加する。
秋の鮮やかな紅葉に彩られた峠道を、心地よい風に吹かれながら、一歩ずつ一歩ずつ自分の足で歩き続け、頂上に辿り着く。
そして、仙丈ケ岳を中心にした雄大な南アルプス連邦と、天竜川を中心に拡がる上伊那地方の裾野が一望でき、天下を取った気分に浸れる。
私は昨年の11月に、県ユースホステル協会主催の、このイベントに参加したけど、峠道が想像していた以上にきつかったぁ~
道幅が狭いうえ、急峻な箇所が多く、昨年の7月豪雨災害で崩落しているところを迂回しなくてはならず、少しは足に自信があったけど、もう十分歩きましたっ! これで結構デスっ! と思った。
それでも、新宿を朝の5時のバスで来たと言う、72歳の山登り大好きおじいちゃんや、小学生の兄弟も参加していて、その人たちに励まされながらどうにか登りきった。
今年も10月21日(日)に開催するとのこと。
足に自信のある方はふるってご参加下さい。
参加費用は3000円で、おにぎりとキノコ汁がふるまわれ、木曽漆器のお椀とお箸のお土産付きです。

木曽へ木曽へとつけ出す米は 伊那や高遠の伊那や高遠の涙米
涙米とはそりゃ情けない 伊那や高遠の伊那や高遠の余り米
と言うのがある。
昔、お米の獲れなった木曽地方へ、伊那の米を馬の背に乗せ、権兵衛峠を越えて運んで行ったことを謡っている。
昨年の2月に権兵衛トンネルが開通して、木曽と伊那は通勤圏内になった。
毎年10月に当市では、往時を偲んで「米の道・権兵衛峠を歩こう」と言うイベントを開催している。
現在はほとんど使われていない、かつての峠道を歩くこのイベントに、県内外から300人以上の人たちが参加する。
秋の鮮やかな紅葉に彩られた峠道を、心地よい風に吹かれながら、一歩ずつ一歩ずつ自分の足で歩き続け、頂上に辿り着く。
そして、仙丈ケ岳を中心にした雄大な南アルプス連邦と、天竜川を中心に拡がる上伊那地方の裾野が一望でき、天下を取った気分に浸れる。
私は昨年の11月に、県ユースホステル協会主催の、このイベントに参加したけど、峠道が想像していた以上にきつかったぁ~

道幅が狭いうえ、急峻な箇所が多く、昨年の7月豪雨災害で崩落しているところを迂回しなくてはならず、少しは足に自信があったけど、もう十分歩きましたっ! これで結構デスっ! と思った。
それでも、新宿を朝の5時のバスで来たと言う、72歳の山登り大好きおじいちゃんや、小学生の兄弟も参加していて、その人たちに励まされながらどうにか登りきった。
今年も10月21日(日)に開催するとのこと。
足に自信のある方はふるってご参加下さい。
参加費用は3000円で、おにぎりとキノコ汁がふるまわれ、木曽漆器のお椀とお箸のお土産付きです。


Posted by mahora at
17:14
│Comments(0)
2007年09月05日
希望学
時代が流れ、社会も変われば、学問の世界も変わる。
以前は考えも及ばなかったことを、まじめに研究する学者も出てくる。
私が今、気になっているのが、東大社会科学研究所の玄田有史の「希望学」です。
若年労働問題のエキスパートで、著書やTV出演も多く、ご存知の方もいると思う。
希望を社会科学する! を枕詞に、2年前から社会や個人の中における、「希望」について、地道な調査を続けている。
労働経済学が専門の学者さんなので、著書全般に、仕事と希望との関係性について書いている。
2001年に出た「仕事のなかの曖昧な不安 揺れる若年の現在」(中央公論新社)では、若年失業者やニート・フリーターについて、バブル崩壊後の失われた10年の中で、中高年の雇用を守るため新規採用を抑えた結果、大量に生み出されたもので、中高年雇用のための犠牲者、として位置づけた。
リストラと言えば、中高年の問題だと思っていたので、詳細なデータから導き出されたこの結論に、ちょっと驚いた。
将来に対する不安材料ばかりが喧伝される今、若者が希望を持ちにくくなっている事は認める。
ただ、さまざまな調査データから、最初から希望通りにいかない人でも、挫折と失敗を繰り返しながら、途中で希望を上手に軌道修正できた人ほど、現在に満足し、自分の存在意義を実感している…と言う結果は興味深かった。
そして、子どものころ親に期待されていた人ほど希望を持ちやすく、モチベーションが衰えない、と言う調査結果も出ている。
希望を持つことは、自己肯定感と直結していると思う。
以前は考えも及ばなかったことを、まじめに研究する学者も出てくる。
私が今、気になっているのが、東大社会科学研究所の玄田有史の「希望学」です。
若年労働問題のエキスパートで、著書やTV出演も多く、ご存知の方もいると思う。
希望を社会科学する! を枕詞に、2年前から社会や個人の中における、「希望」について、地道な調査を続けている。
労働経済学が専門の学者さんなので、著書全般に、仕事と希望との関係性について書いている。
2001年に出た「仕事のなかの曖昧な不安 揺れる若年の現在」(中央公論新社)では、若年失業者やニート・フリーターについて、バブル崩壊後の失われた10年の中で、中高年の雇用を守るため新規採用を抑えた結果、大量に生み出されたもので、中高年雇用のための犠牲者、として位置づけた。
リストラと言えば、中高年の問題だと思っていたので、詳細なデータから導き出されたこの結論に、ちょっと驚いた。
将来に対する不安材料ばかりが喧伝される今、若者が希望を持ちにくくなっている事は認める。
ただ、さまざまな調査データから、最初から希望通りにいかない人でも、挫折と失敗を繰り返しながら、途中で希望を上手に軌道修正できた人ほど、現在に満足し、自分の存在意義を実感している…と言う結果は興味深かった。
そして、子どものころ親に期待されていた人ほど希望を持ちやすく、モチベーションが衰えない、と言う調査結果も出ている。
希望を持つことは、自己肯定感と直結していると思う。

Posted by mahora at
17:30
│Comments(0)
2007年09月04日
青パパイヤ
先日行ったグリーンファームで、青パパイヤを買ってきた。
青パパイヤには、たんぱく質分解酵素のパパインが豊富で、ビタミンCもあり、夏バテ料理にはもってこいです。
少し硬めのお肉も、青パパイヤをすりおろした中に漬けておくと、軟らかくなり、歯の悪い高齢者でも美味しくいただけます。
グリーンファームの青パパイヤは、沖縄の那覇から東へ、船で13時間、または飛行機で1時間の、太平洋上に浮かぶ南大東島のものです。
この青パパイヤが結ぶ縁で、夏になると、南大東島の子どもたちでつくる「大東太鼓碧会」と、民謡グループ「ボロジノ娘」の小中学生たちが当市を訪れ、文化会館でコンサートを開催し、多くの市民が聴きに行く。
島民人口わずか、1300人あまりの小さな島で、サトウキビと台風の通り道としてのイメージしかなかったけど、海の男らしい陽気で力強い太鼓演奏と、どこまでも続く紺碧の海と、はるか彼方の水平線が目の前に拡がるような、伸びのある澄んだ歌声が素晴らしいです。
青パパイヤのパパイン酵素同様、少し固くなりかけた私の頭も心も、やさしく柔らかにしてくれました。

青パパイヤには、たんぱく質分解酵素のパパインが豊富で、ビタミンCもあり、夏バテ料理にはもってこいです。
少し硬めのお肉も、青パパイヤをすりおろした中に漬けておくと、軟らかくなり、歯の悪い高齢者でも美味しくいただけます。
グリーンファームの青パパイヤは、沖縄の那覇から東へ、船で13時間、または飛行機で1時間の、太平洋上に浮かぶ南大東島のものです。
この青パパイヤが結ぶ縁で、夏になると、南大東島の子どもたちでつくる「大東太鼓碧会」と、民謡グループ「ボロジノ娘」の小中学生たちが当市を訪れ、文化会館でコンサートを開催し、多くの市民が聴きに行く。
島民人口わずか、1300人あまりの小さな島で、サトウキビと台風の通り道としてのイメージしかなかったけど、海の男らしい陽気で力強い太鼓演奏と、どこまでも続く紺碧の海と、はるか彼方の水平線が目の前に拡がるような、伸びのある澄んだ歌声が素晴らしいです。
青パパイヤのパパイン酵素同様、少し固くなりかけた私の頭も心も、やさしく柔らかにしてくれました。


Posted by mahora at
17:19
│Comments(2)